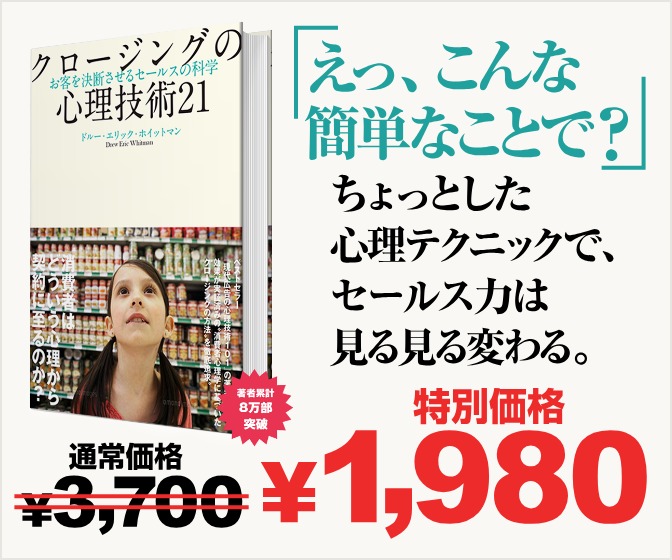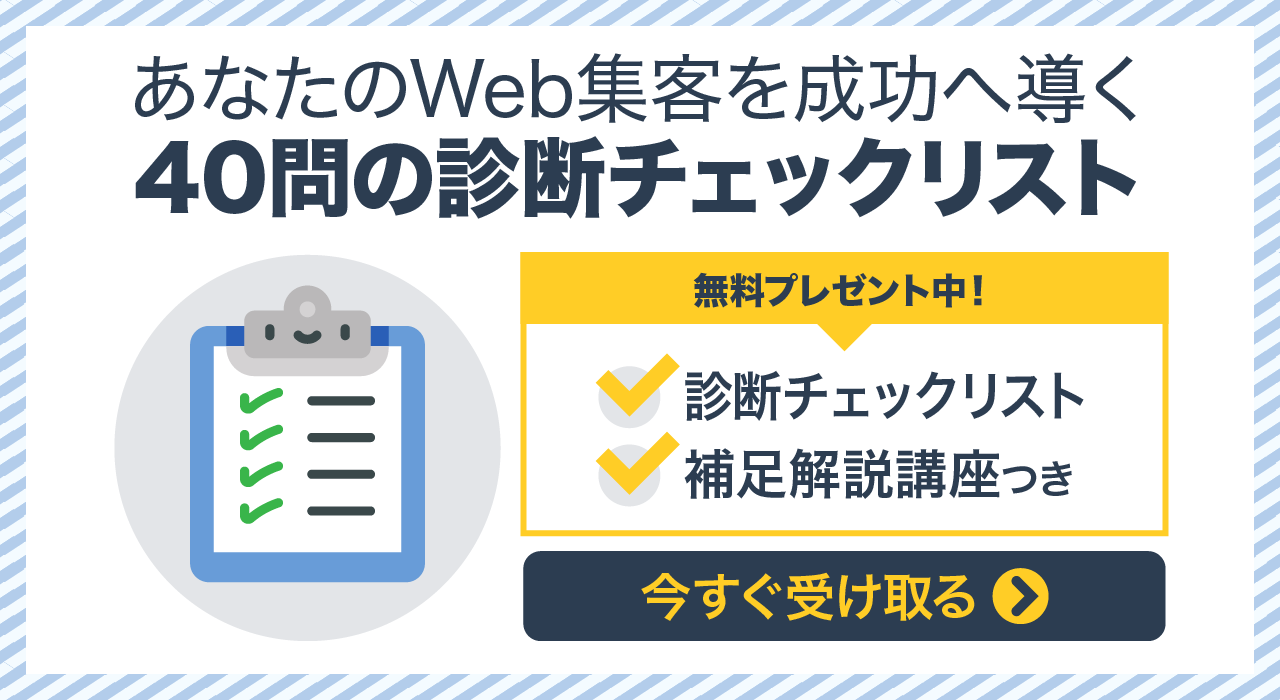第三者の言葉を信じやすくなる心理現象を、ウィンザー効果と言います。あなたも一度はクチコミサイトで、飲食店の評価を調べたことがあるのではないでしょうか?
クチコミの評価が高ければ安心しますし、低ければちょっと不安な気持ちになりますよね。
あなたが商品を販売する際には、ウィンザー効果をマーケティングに利用することができます。その方法は、まだお客さんになっていない人からの信頼度をアップさせるために、広告やWebサイトに「お客さまの声」を掲載することです。
クチコミ効果とも呼ばれるこのウィンザー効果は、ただポジティブなコメントを掲載すれば良いというわけではありません。
クチコミ効果を最大限に発揮するためには、ウィンザー効果の正しい使い方を知っておいてください。
スポンサード リンク
ウィンザー効果 とは
ウィンザー効果(Windsor effect)とは、クチコミやレビューなど第三者から間接的に情報が伝わることで、信ぴょう性や信頼性が増す心理効果です。
例えば、Aさんが自分自身で「私は頭が良くて優秀です」という言葉よりも、Bさんが言う「Aさんは頭が良くて優秀です」の言葉の方に信ぴょう性を感じやすいということです。
「私は優秀です」なんて聞くと「おいおい、自信過剰な奴だな」と感じてしまいますよね。
多くの広告宣伝では、自分で自分を「いい商品です」と言っています。これを第三者の口から「あの商品はいいですよ」と言ってもらえば、広告としての信頼性が増すというわけです。
ウィンザー効果の由来
ウィンザー効果の「ウィンザー」とは、アーリーン・ロマノネス著のミステリー小説『伯爵夫人はスパイ』に登場する、ウィンザー公爵夫人のセリフに由来すると言われています。
「第三者の褒め言葉は、どんなときでも一番効き目があるのよ。忘れないでね。いつかきっと役に立つわ。」
本人から直接褒められると、嬉しいと同時に「大げさに言ってくれてるのかな」と感じたり、場合によっては「何か裏があるのかな?」と勘ぐったりすることもありますよね。
ですが、第三者から「あの人があなたのこと褒めてたよ」って言われると、なんだか素直に受け取れる気がします。
なぜ第三者の言葉には、信ぴょう性があるのでしょうか?
スポンサード リンク
ウィンザー効果が起こる2つの理由
ウィンザー効果が起こるには、2つの理由が考えられます。
- 利害関係がない
- 人数が多い
1. ウィンザー効果は「利害関係がない」ことで起こる
まず1つめに、ウィンザー効果は、友人間でのうわさ話や商品レビューには「利害関係がない」ことで起こります。
当人が発信する情報の場合は、自分の利益のために誇大されている可能性があります。ですが、利害関係のない第三者が発信する情報には、ウソの可能性がないと感じます。
例えば、AさんとBさんの間に利害関係がないのなら、Bさんが発言する「Aさんは優秀です」という言葉は、公正なジャッジに感じます。なぜなら、ウソをつく理由がないからです。
AさんとBさんがすごく親しくて、Aさんを褒めることでBさんが何らかの利益を受け取ってそうだとしたら、信ぴょう性はなくなりますよね。
ですので、例えばC社が「D社の商品はここがダメ」とライバル社を評価しても、ライバル社を悪く言うことでC社に利益が入るように感じるために、ウィンザー効果は起こりません。
反対に、C社が「D社の商品はここが素晴らしい」とライバル社を評価すれば、ライバル社を褒めることでC社に利益がないと感じるために、ウィンザー効果が起こります。(大げさに褒めたとしたら、勘ぐるかもしれませんが)
2. ウィンザー効果は「人数が多い」ことで起こる
2つめに、ウィンザー効果は、第三者からの情報の数が多いことで起こります。
人は自分の意見よりも、集団の意見の方が正しいと考える傾向があります。
例えば、自分が「白」だと思っているモノを、2〜3人が「あれはグレーですよ」と言った場合は、「いや、白だと思うよ・・・」と自分の意見に疑いを感じません。
ところが、100人が「あれはグレーですよ」と言えば、自分だけが知らない何かがあって、自分の意見が間違っているんじゃないかと不安になります。そして、「確かにグレーなのかも」と考えるようになります。
このような現象は、集団心理における同調現象と呼ばれます。多くの人が支持することで同じことをしようと考える心理現象は、バンドワゴン効果と言います。
ウィンザー効果も、自分が知っている情報よりも、多くの人が知っている情報の方がより詳しくて正しいように感じやすく、他人の情報の影響力が増すことになります。
マーケティングでのウィンザー効果の使い方
商品販売の際には、セールスレターや販売ページ(ランディングページ)に「お客さまの声」を載せることで、商品に対する信頼度を上げることができます。
お客さんの声はなるべく多く掲載する
お客さんの声は、なるべく多く掲載した方が、より信頼度も上がります。
先ほどお話ししたとおり、2〜3人の意見よりも、100人の意見の方がウィンザー効果が起こりやすくなるからですね。
本物の声であることを証明する
ただし、ウィンザー効果を正しく使うためには、「利害関係がない情報源」であることが大切です。お客さんの声が販売者の手によって操作されているように感じたとしたら、ウィンザー効果は働きません。
例えば、お客さんの声が全てニックネームや仮名であったり、文面がテキスト表示のみである場合には、販売者が自作自演しているように感じる場合があります。
ウィンザー効果を正しく働かせるためには、なるべくお客さんの写真と直筆の手紙、実名を掲載することが大切です。
お客さんの声を選別する
また、お客さんの声が全て同じような内容で、商品を褒めちぎっていたとしたら、たとえ本当にお客さんからいただいた声でも不信感が生まれる場合があります。
さらに、一人のお客さんが商品の良いところをあれもこれもと褒めてくれた場合には、メッセージをできるだけシンプルにして、どれか一つに絞るようにします。
「お客さまの声」を読む人に、届けたいメッセージを理解しやすくするためです。
正しい「口コミ効果」の扱い方
お客さんの声の正しい扱い方をまとめると、次のとおりです。
- お客さんの声はなるべく多く掲載する
- なるべく実名を載せる
- なるべく顔写真を掲載する
- なるべく直筆の手紙を掲載する
- 1つの声のうち、1つのベネフィットに焦点を当てる
- 違うベネフィットについての声を多く掲載する
- たとえ本当の声でも、ウソくさい声は載せない
まとめ
ウィンザー効果とは、当事者から発信する情報よりも、第三者から間接的に伝わる情報の方が、信ぴょう性や信頼性が高くなる心理現象のことです。
ウィンザー効果をマーケティングで扱うためには、ただポジティブな評価を掲載するのではなく、本当のことを言ってそうなクチコミを選ぶことも大切です。
アメリカのある通販番組では、消費者が商品を使用したインタビューの時間の長さを、番組時間の25%、50%、75%でテストしたところ、75%にしたものが一番売れ行きが良かったといいます。
正しいクチコミは、載せれば載せるほど信頼性が高くなるということですね。
さらに心理学をマーケティングに応用する方法は、こちらを参考にしてください。
-
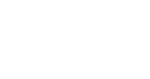
マーケティング心理学|今すぐ顧客心理を掴むテクニック【37選】
マーケティングの効果を高めるためには、人間の心理や思考のクセ、脳の特性を知ることが大切です。 なぜなら、たったひと言の違いでも、人の行動は変えられるからです。何をどんなタイミングで言えば良いのかは、心 ...
続きを見る
スポンサード リンク